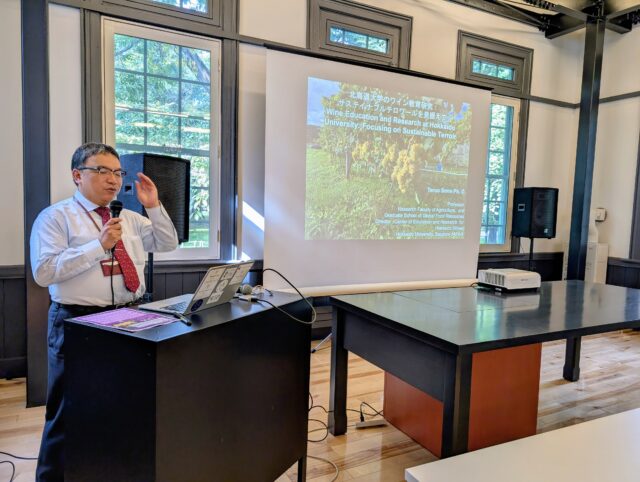メルボルン大学とのワイン研究ワークショップを開催
9月26日(金)、北海道ワイン教育研究センターにおいて、北海道大学の戦略的国際パートナーである豪州メルボルン大学とのワイン研究に係るワークショップを開催しました。本ワークショップは、北海道ワイン教育研究センターの曾根輝雄センター長とメルボルン大学教養学研究院のジャクリーン・ダットン研究担当副研究院長のピノ・ノワール生産地域における「テロワール、(豪先住民の文脈での)カントリー、風土」への関心によるもので、気候変動とともに変化しつつある両国のワイン生産地とアカデミアを繋ぐ枠組みのキックオフ・イベントとなりました。
ダットン副研究院長は、文化的・科学的視点からピノ・ノワールの魅力と課題を探求する国際知識交流拠点事業「ザ・ピノ・ノワール・プロジェクト」の長を務めており、豪国内外のシンポジウムやフェスティバルに関わるフランス学・美食学者です。同学理学研究院から、デジタル農業・食銀科学の専門家であるシグフリード・フエンテス准教授とクラウディア・ゴンザレス・ビエホ・デュラン研究員、食品科学・ワイン学のパンチェン・チャン上席講師も迎え、日本側からはNPO法人ワインクラスター北海道の阿部眞久代表理事を招き、国際連携推進本部の植村妙菜学術主任専門職の通訳のもと、様々な切り口からのワイン研究を市民へ示す機会となりました。
今般はワインの中でも歴史が長く、土地の個性を忠実に表現する品種であり、高価格帯のワインとして特別な地位を確立した今、気候変動と世界市場の変容を受けて、比較的世界中に生産地が広がっているピノ・ノワールを中心に据えています。曾根センター長からは、北海道ワインの一大生産拠点である余市町と協働し、地域と大学の一体的な動きで地域と生産者に貢献する持続可能なテロワールを目指す、センターの取り組みが紹介されました。阿部代表理事からは、北海道ワイン株式会社から独立したシニアソムリエの視点から、この25年間の北海道におけるピノ・ノワール生産、他品種を含めた生産量の移り変わり、温暖化の影響が説明されました。
ダットン副研究院長からは「豪州先住民にとって、大文字で始めるCountry(カントリー)には、国ではなく、英単語では表せない、土地・水域・海といった環境から、家族、慣習、文化、人がその土地に帰属することまで大きな意味があり、同じピノ・ノワール生産地でもフランス、豪州、日本でテロワールへの考え方は異なっている」ことについて講演がありました。フエンテス准教授からは、「Irrimax(土壌の湿潤・栄養パターンを見るアプリ)」、「Inspector Paw(病害虫発見のための小動物バイオメトリクス用アプリ)」、「VitiCanopy(ワイン用ブドウの樹勢と空隙率の推定アプリ)」、「BioSensory(官能評価中の生理・感情反応測定アプリ)」、低コスト電子鼻やAI、ドローンを活用した「ワインやビールの香り特性評価」、「ブドウにおける煙害検出と、ワインに残る煙臭評価・予測」、豪州研究会議(ARC)センター・オブ・エクセレンス事業に採択された「Plants for Space(P4S;宇宙のための植物)」など、気候変動に強い生産体制を構築するための種々の低コストのデジタルツール開発の紹介がありました。
一行は、平川ワイナリー、宝水ワイナリー、山崎ワイナリーなど余市、空知地方のワイン生産地も訪れ、ランギアン期の川端層、トートニアン期の岩見沢層といった古代の地層による土質、ミネラル分の違いからのブドウ品種選択やワインの質感を観察し、生産者との対話を楽しみました。広く美食学や文化的イベントにも繋げることを踏まえ、大学院生の共同教育・研究滞在の可能性も話され、初のワイン研究におけるワークショップは成功裡に終了しました。